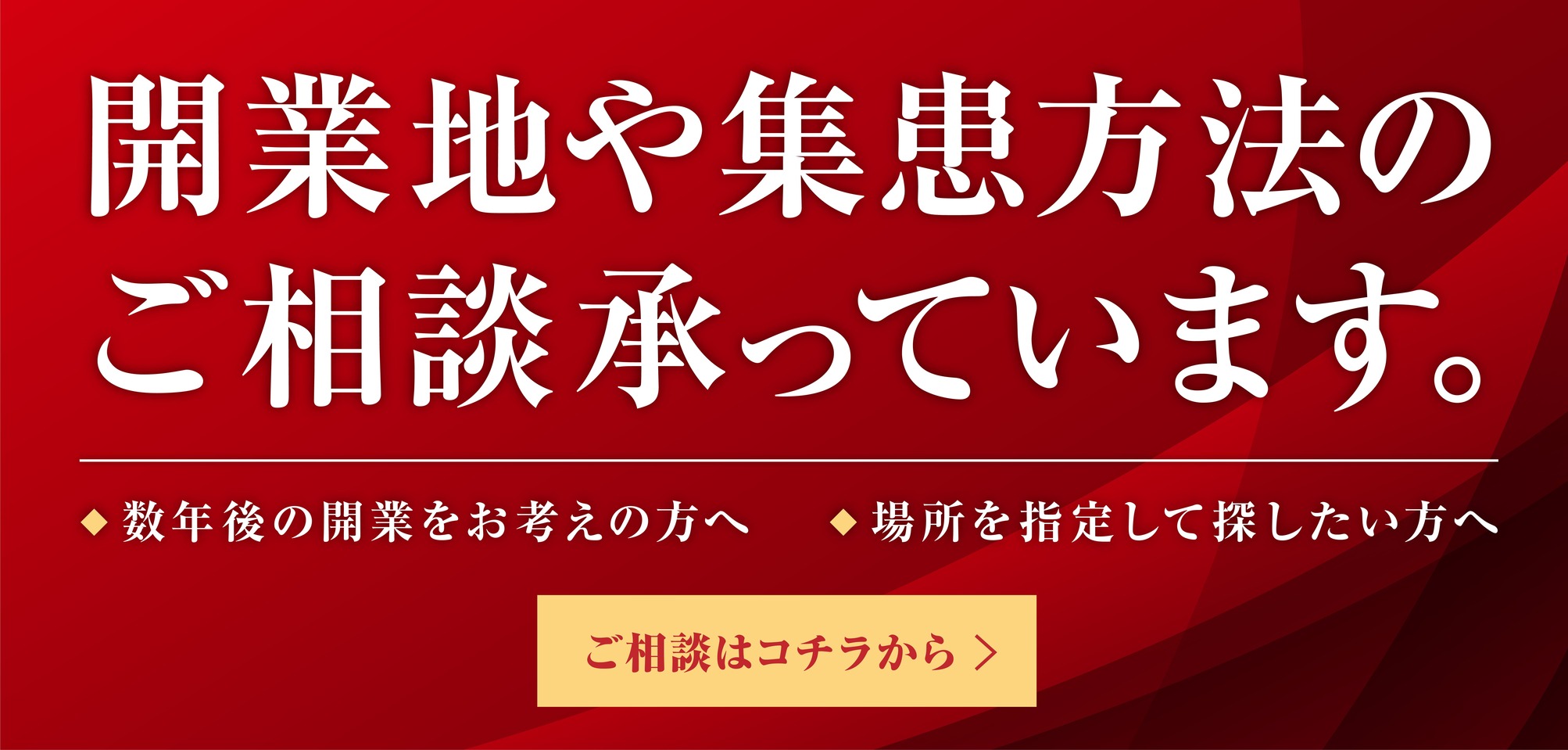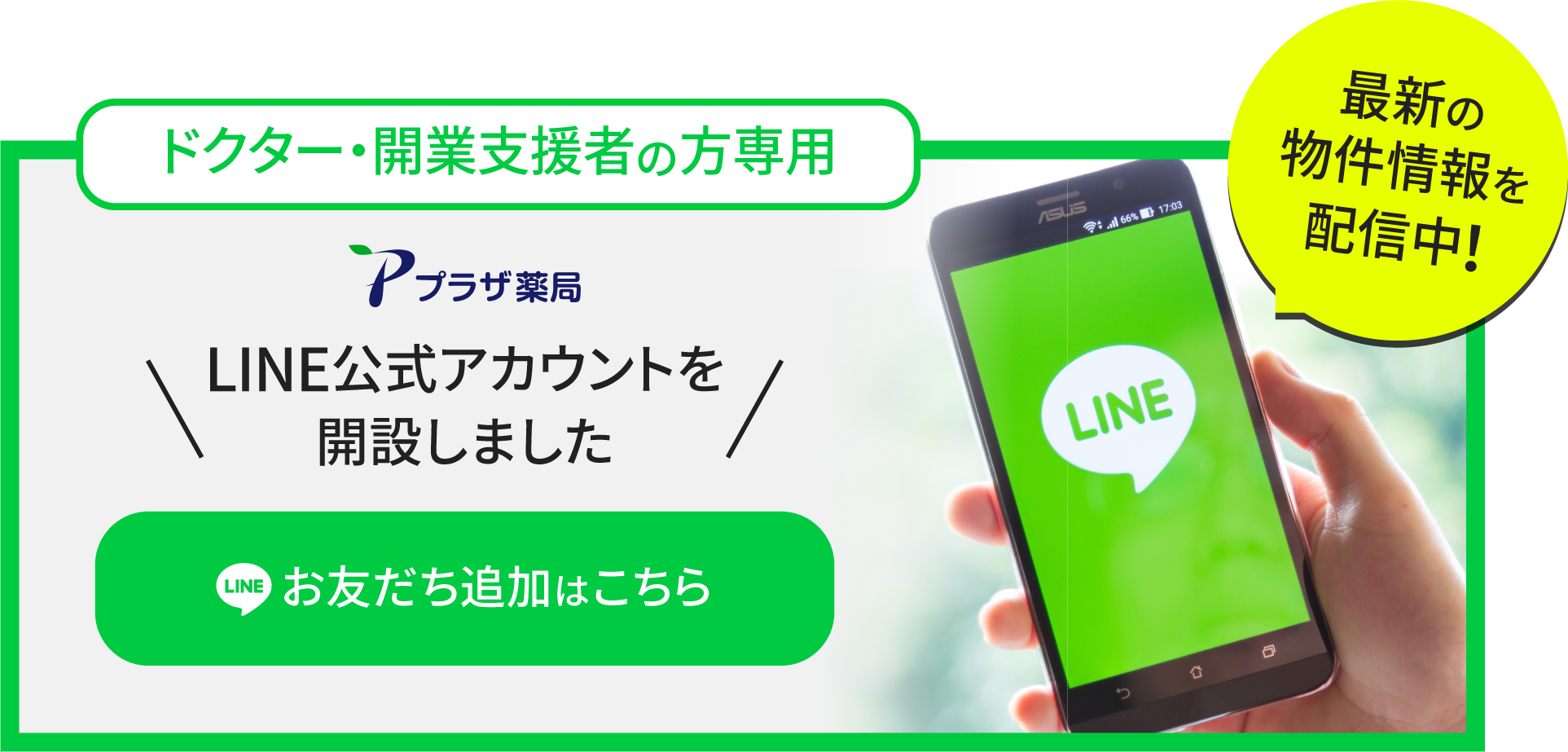医療モールが地域医療を支える5つの理由と今後の展望

近年、医療モールの開業が増加しています。その背景には、高齢化による医療費の増加が続いている状況に対し、それを少しでも緩和させようという国の政策があります。国は、中核病院の病床数を削減して不必要な入院を減らし、重篤および重症者の治療に対する高度な医療技術の提供に専念することで医療費を少しでも削減しようと取り組んでいるのです。その政策により、診療所はこれまで以上に地域医療を支えるという大きな役割を担うこととなり、その役割を果たすための解決策として医療モールの活用が期待されています。
この記事では、今注目されている医療モールが地域医療を支える5つの理由と今後の展望についてご紹介します。
医療モールの定義と特徴
医療モールとは一体どのような施設なのでしょうか。
診療所目線、患者目線、それぞれから見た医療モールの特徴とともにご紹介します。
医療モールの定義
医療モールとは、様々な診療科の診療所と調剤薬局が1つの建物やエリアなどに集合している医療施設のことをいいます。「医療モール」といっても種類は複数あり、1つのエリア内に複数の戸建て診療所が集まる医療ビレッジや医療ドミナント、ビル内に診療所が集まる医療ビル、施設に併設されている医療モール(商業施設併設)、レジデンス併設型、オフィス併設型などが代表的な例です。
医療モールの特徴
*診療所側から見た特徴
個別で開業するよりも認知されやすいため効率的に集患できる点や、トイレや休憩所、駐車場などの施設を共有することによって初期費用やランニングコストが下げられる点に特徴があります。
また、同じ医療モール内のほかの診療科と情報を共有し連携をとることで、患者さんにより適切な医療を提供できるというメリットもあります。
*患者さん側からみた特徴
複数の診療科を受診する必要がある場合、移動する手間が省けるので利便性が非常に高いです。また、商業施設併設型であれば買い物や食事のついでに診療を受けたり、オフィス併設型であれば仕事の合間や出勤前後に診療を受けたりといったように、医療モールの種類によっても様々な利便性の高さを感じることができます。
同じ医療モール内の複数の診療所を受診することによって、複合的な医療サービスを受けることができる点も大きなメリットです。
地域医療を支えると言われる理由
医療モールが地域医療を支えるといわれる理由には大きく5つあります。
それぞれについてご紹介していきます。
総合的な初期医療と専門医療の提供
医療モール内の診療所では、その診療科のプロフェッショナルが医療を提供してくれています。個別開業の状況においては専門医療といっても点での対応となってしまいますが、その専門医療を提供してくれる診療所が一つのエリアに集まることによって、総合的な医療サービスを提供することが可能となります。中核病院のように機器が揃っているわけではなく、大掛かりな手術が行えるわけではありませんが、医療モールは総合的な初期医療の提供施設として機能することができます。
医療資源の効率的な活用
日本の人口の大部分を占める地方中小都市圏において、医療サービスは高密度で提供されている地域と低密度でしか提供されていない地域とに分かれています。1980年台からの数十年で100 床未満の小規模な病院が増加しましたが、この規模の病院では人員の確保が難しい上に、地域の医療需要が十分ではないケースもあり、結果として一部の診療科を廃止したり廃業したりといったケースも多く見られました。医療サービスが十分に提供できない病院が分散するよりも、利便性の高いエリアに医療資源を集めて効率的に活用することによって質の高い医療サービスの提供を実現することができると考えられ、医療モールはその一つの形です。小規模病院が分散することは一見利便性が高そうに見えますが、距離アクセス上の負担が増加したとしても、必要な診療科が揃っており、十分な質を確保できる医療サービスを提供してくれる施設が存在していることの価値が高いといえます。
地域包括ケアシステムへの対応
厚生労働省が発表している「地域包括ケアシステム」への対応も医療モールの大きな役割です。「地域包括ケアシステム」とは、高齢者などの生活上の安心、 健康の確保、自立生活の支援を目的として、可能な限り住み慣れた地域で医療や介護、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスを、サービス利用者の選択に基づき適切に提供できる体制をもつシステムといえます。
このシステムは、単体の診療所だけで実現することはできません。様々な診療科や調剤薬局が集まる医療モールが中心となり、介護・福祉施設、フィットネス施設、高齢者住宅などの多彩な施設が協力しあうことが求められます。
医師の開業ニーズへの対応
少子高齢化が進む日本では年々人口が減少していますから、当然患者数も減少していっています。一方で医師の人数は増加傾向にありますが、前述の通り、国の政策で膨らむ医療費を削減することを目的に病床の削減を進めています。病床の数が減れば、当然その病院で必要となる医師の人数は減少しますから、これまでであれば中核病院へ就職を希望していた医師が就職できなくなり、別の手段として開業という選択をせざるを得なくなっています。
診療科にもよりますが医師の供給過多が起こっているため、開業すれば必ず集患できるわけではないという厳しい状況だといえます。こうした医師の開業先として注目されているのが、医療モールというわけです。医療モールで開業すれば、個人開業よりも効率的に集患することができます。
患者の利便性向上と集患効果
複数の診療科を受診する必要がある人にとって、医療モールは非常に利便性が高い施設です。特に高齢になるにつれてお世話になる診療科は増加する傾向にあり、診療所間の移動は身体的な負担になりやすいですから、より歓迎されるといえます。また、自分の病状や飲んでいる薬を的確に伝えることが難しくなってきても、医療モール内の診療所間で情報共有がなされることにより、スムーズに医療サービスを受けることができます。
医療モールの立地条件についても、患者の利便性向上に関係しています。例えば、商業施設に併設されている場合は、診療のついでに買い物を済ますことができますし、時間が遅くなれば食事をして帰ることも可能。送迎や付き添いの目的で来訪した家族の待ち時間を有効に使うこともできます。オフィスやマンションに併設されていれば、通院が格段に楽になるでしょう。広い共有の駐車場が併設されていれば、車社会であっても通院がしやすくなるということもあります。
こうした利便性の向上は地域医療を活性化させますので、集患にも効果的であるといえます。
医療モールの今後の展望
医療モールは、一度に複数の診療科を受診できる利便性の高い医療施設であるというだけでなく、地域医療を支える基盤としての活用が期待されています。
まずは、これまでは入院しながら療養していた人が安心して在宅療養できるような医療サービスを提供すること、総合病院をかかりつけ医としていた人がスムーズに医療サービスを利用できるようにすることが必要ですが、それだけではこれからの時代の地域医療を十分に担っているとはいえません。在宅医療を充実させたり、介護事業所や高齢者施設との連携を強化したりといったことも必要です。また、高齢者を中心とした医療や介護だけではなく、子育てや教育をサポートできるようなサービスとの連携も期待されます。医療モールはより地域に溶け込み、医療と健康を中心として地域コミュニケーションを活性化させる役割もになってるといえるでしょう。これからの社会において、老若男女問わず全ての人がより安心してより健康に生きていくための大きな力となることが期待されます。
まとめ
日本は超高齢化社会に突入しました。同じ医療システムのままであれば、国の財政はさらに苦しくなっていき、現在のような医療保険システムを維持できなくなる恐れがあります。もし医師が高度な医療サービスを提供できるだけのスキルを持っていたとしても、そのサービスを広く提供できる環境がなければ、多くの人を救うことは難しくなってしまいます。
必要な時に、必要な場所で、必要な人が、必要な医療サービスを受けられる世の中を作っていくためにも、地域包括ケアシステムへの対応が急がれます。その中心となれるポテンシャルを持っているのがこの医療モールであり、今後の展開が期待されているのです。