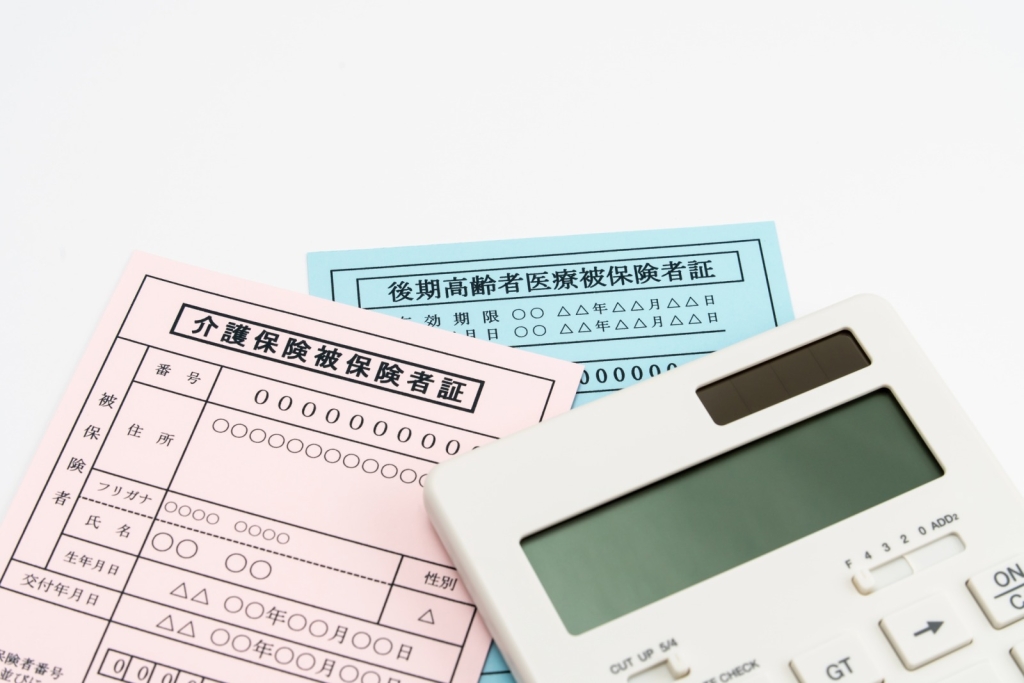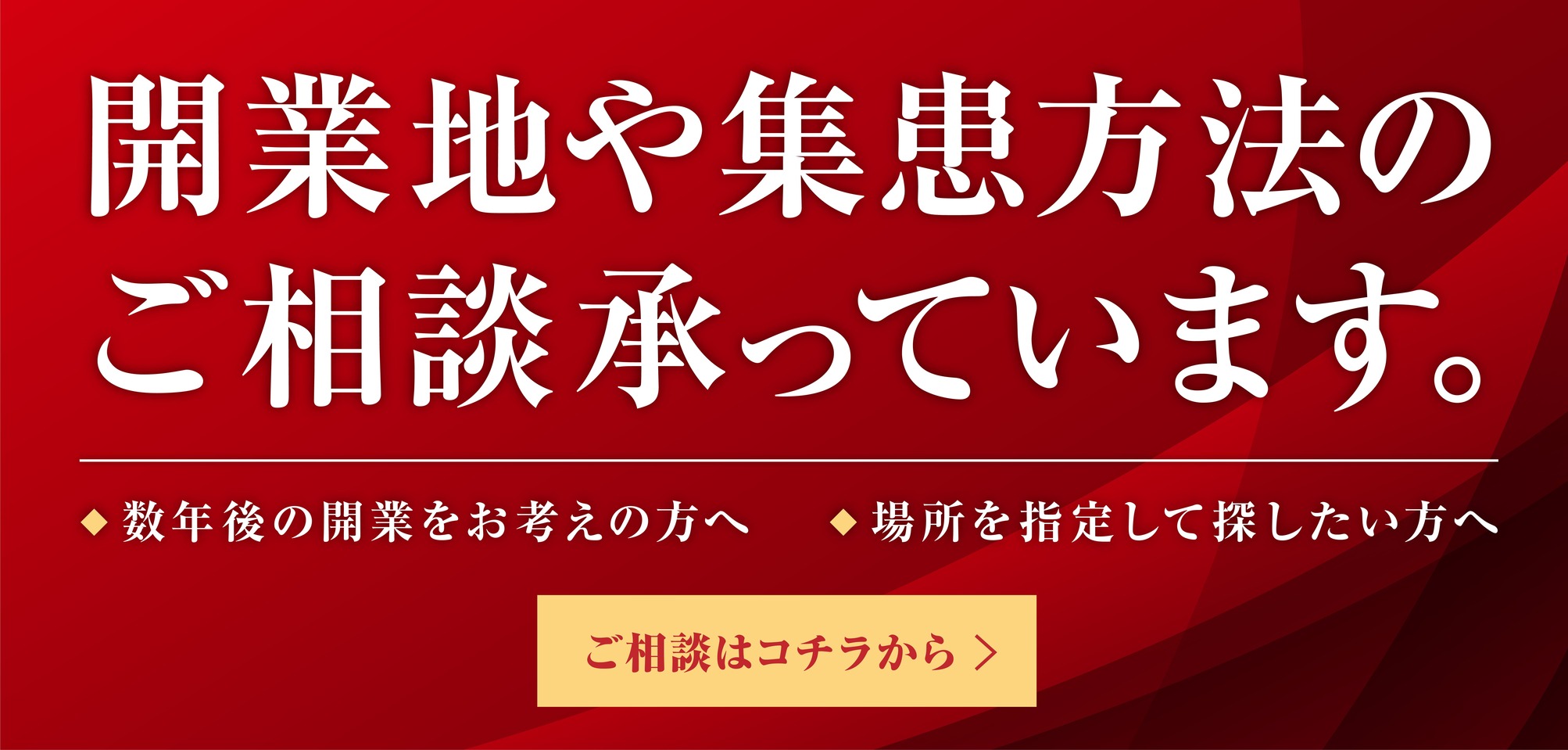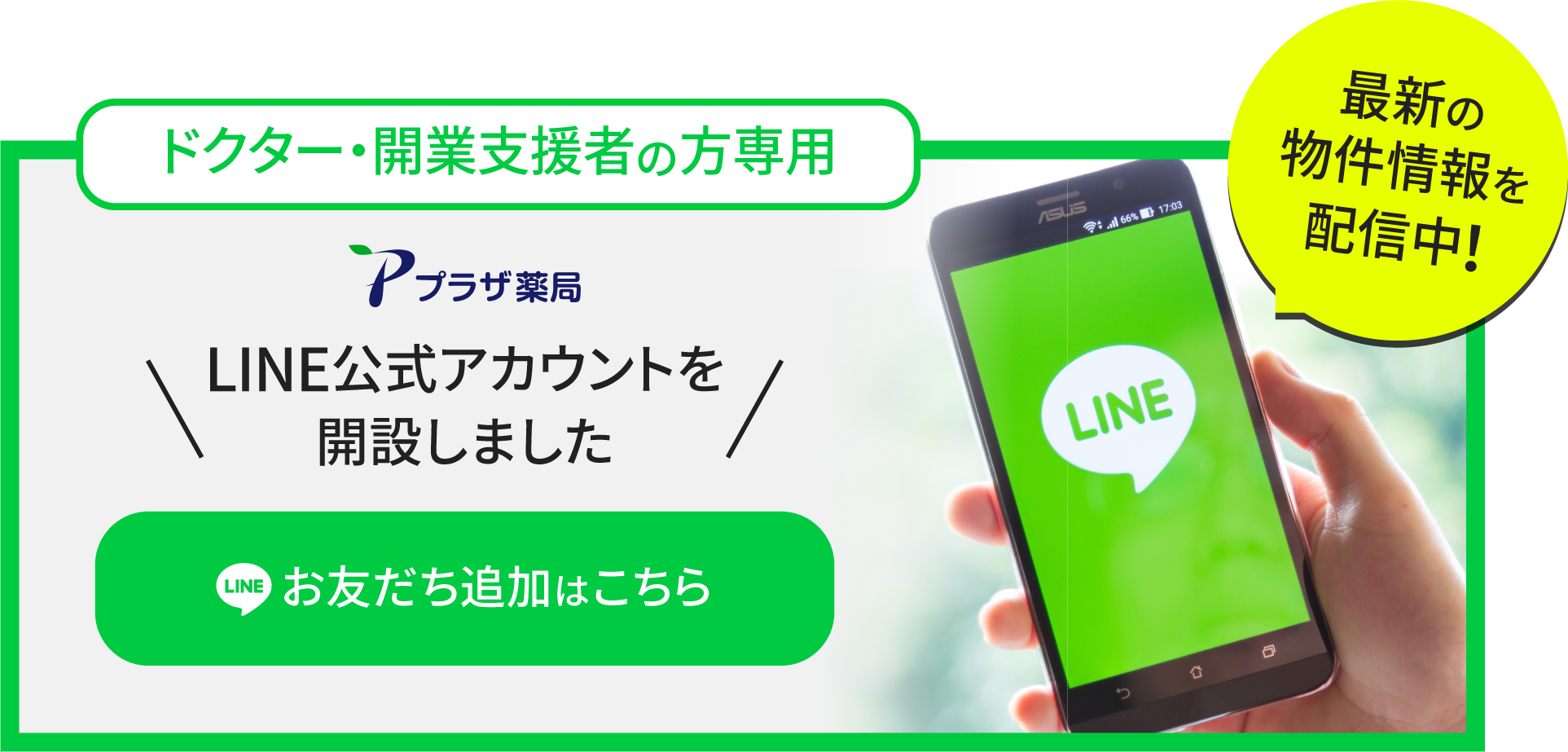医療モール(クリニックモール・メディカルモール)で医院開業するメリット・デメリット
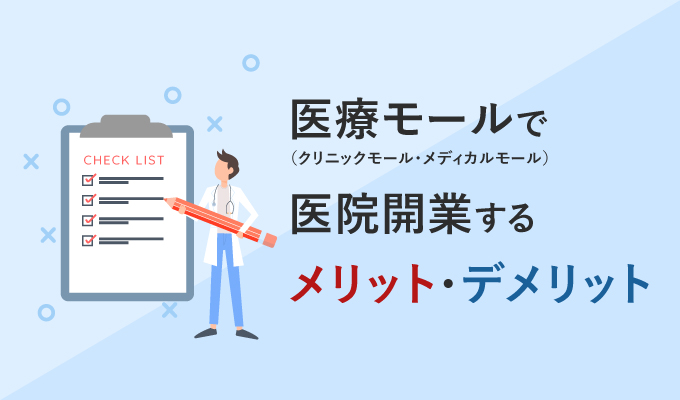
近年、さまざまな診療科が1つの場所で集患する形の「医療モール」が増加しています。この医療モール内で開業を検討している医師の方もいらっしゃるのではないでしょうか。医療モールと一口にいっても複数のタイプがあり、どのタイプが適しているのかを判断するのは難しいです。医療モールは、患者さんにとって利便性が高く、集患も見込まれるので医師にとっても魅力的な医療施設といえますが、具体的にどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
この記事では、医療モールが増加している理由や背景をもとに、医療モールで診療所(クリニック・医院)の開業をお考えの医師の方に向けて、医療モールのタイプや各タイプごとのメリットとデメリットについてご紹介していきます。
医療モールの6つのタイプ
医療モールとは、クリニックモールやメディカルモールとも呼ばれ、内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、整形外科、心療内科、婦人科、脳神経外科など診療科の異なる診療所や調剤薬局が1つの建物内もしくは同じ場所に集合している医療施設のことです。
医療モールと一口にいってもいくつかタイプがあり、大きく分けて以下の6つに分類されます。
医療モールの分類
- 医療ビレッジ
- 医療モール
- 医療ビル
- レジデンス併設型
- オフィス併設型
- 医療ドミナント
医療ビレッジ
「医療ビレッジ」は、同じ敷地内に戸建てタイプの診療所と調剤薬局が集合しています。それぞれ個別の建物ではありますが、内外装が統一されているケースもあります。外装のイメージはある程度統一されていても、建物自体の設計や内装の自由度が高いケースや、内外装ともに自由度が高く、新しく開業する医師のコンセプトやイメージに合った施設の建築が可能なケースもあります。
比較的大きな道路沿いや土地にゆとりのある場所にあり、各クリニックが個別の駐車場を保有するケースは少なく、広い共有の駐車場を保有しているケースが一般的です。
医療モール
駅ビル内や郊外にあるショッピングモールなど商業施設の一角に、診療所が集合するエリアが併設されているスタイルが「医療モール」です。
ショッピングモールは地域のランドマーク的な立ち位置で親しまれていることも多く、買い物に来た方に無意識に認知されやすい特徴があります。ショッピングモールには食料品店や衣料品店、レストランなどが入っているため、買い物のついでに気軽に通院したり診療後に食事をして帰ったりできて患者さんにとっての利便性が高いですし、同伴できた家族の時間潰しにも最適です。
医療ビル
1つのビル内に複数の診療所と調剤薬局がはいっているのが「医療ビル」です。
医療ビルは設計段階から医療機関が入る前提で建物が作られているので、段差の少ないバリアフリー設計になっていたり、車椅子の利用を前提としたエレベーターやトイレになっていたりと、医師や患者さんにとって使いやすいきめ細やかな設備を整えた設計となっています。電気容量や給排水のインフラについても、通常のビルよりも充実していることが多いです。
レジデンス併設型
マンションの低層部に複数の診療所が併設されたマンション内医療モールが「レジデンス併設型」と呼ばれます。特にマンション住人にとって利便性が高く、マンションの規模が大きければ大きいほど集患ができる可能性が高いです。ただし、マンション住人以外にも来院してもらう必要がありますので、マンション内に医療モールがあることが分かりやすいように設計されていることが望ましいです。道路際の看板などに加え、近隣にチラシを配るなどの広報活動も重要となってきます。
オフィス併設型
「オフィス併設型」は、複数のオフィスが入居しているビルの中にあるタイプの医療モールです。仕事の合間や終業前後にも通いやすいため、同ビル内のオフィスに勤務する人はもちろん、近隣のオフィスワーカーにとっても非常に便利です。駅に近い場合はビル外からの集患も大いに期待できます。定期的にお薬を貰わなければならないような慢性的な疾患をお持ちの患者が多い場合、その利便性はより高まるでしょう。
医療ドミナント
開業している診療所の敷地に隣接した土地に、異なる診療科が新たに開業し、実質的に数件の医療関係施設が集まる地帯を「医療ドミナント」と呼びます。医療ビレッジのように医療モールとしての機能を備えてスタートしているわけではありませんが、結果的に診療所同士が連携を取りやすく医療モールとして機能します。複数の診療所を訪れなければならない人にとって利便性が高いといえます。
タイプ別医療モールのメリット・デメリット
医療モールは、個別に戸建てやビル内で開業する場合と比較して認知されやすく効率的に集患できる点に大きなメリットがあります。治療内容によっては他の診療科での治療が必要になるケースも発生しますが、医療モールであれば連携が取りやすいという点もメリットでしょう。費用面において、トイレや休憩所、駐車場などの施設を共有できるケースも多く、初期費用やランニングコストを下げられる可能性が高いです。
一方で、医療モールは複数のクリニックが使用する目的で作られているため、設備やデザインを自由に決められなかったり、一定のルールに沿って運営しなければならなかったりします。他の医療施設と連携を取れることがメリットではありますが、独立開業して自由にやっていこうと考えている方にとっては人間関係の煩わしさを感じてしまうケースもあるようです。医療モールによっては費用が割高になることもありますので、どんな医療モールに開業するかはよく検討する必要があります。
このように医療モールにはメリットとデメリットがあります。
この章では医療モールのタイプ別のメリット・デメリットについても詳しくご紹介していきます。
医療ビレッジ
*メリット
医療モールの中でも、医療ビレッジであればある程度設計やデザインに自由度があります。診療所のコンセプトやイメージを形にしたい場合は、より自由度の高い医療ビレッジを探すとよいでしょう。
共有の駐車場がある場合が多いので、車移動がメインとなるエリアでの開業を目指す場合には大きくコスト削減ができます。
*デメリット
共有施設の利用によりコスト削減はできるものの戸建てタイプになりますので、開業費用は他のタイプと比べて高くなります。
医療モール
*メリット
ショッピングモールなどの商業施設自体の認知度があるため、医療モールとしての認知度も高くなりやすいです。買い物や食事などのついでに来院できる利便性は大きなメリットです。
*デメリット
併設されている商業施設の評判に集患が左右されてしまう可能性があります。他の商業施設ができたり、施設の老朽化が進み集客力がダウンすると、集患力も同時にダウンしてしまう可能性が高いです。
医療ビル
*メリット
ビル自体が医療機関向けになっている点が大きなメリットです。特に電力消費が大きい診療科など、医療機関特有のインフラ設備が必須の場合はメリットが大きいでしょう。
*デメリット
医療ビルに限ったことではありませんが、医療モールは個別の診療所の評判だけではなく、医療モール全体の評判も診療所の集患に影響します。医療ビルは医療施設だけで構成されている分、医療モールとしての評判に影響されやすいといえます。
レジデンス併設型
*メリット
居住しているのと同じ建物内に診療所があるというのは非常に利便性が高いので、マンション規模が大きければ大きいほど集患しやすいといえます。周辺にも住宅街が広がっているケースが多いので、認知度が上がればさらなる集患も期待できます。
*デメリット 医療モールが目立たず、単なるマンションと認知されてしまうとマンション外からの集患が難しくなります。認知度を高めるための工夫が必要といえます。
オフィス併設型
*メリット
オフィスワーカーにとって利便性が極めて高く、一定の年齢層の集患に大いに期待できます。
*デメリット
オフィス街では日中勤務の方がほとんどのため、昼休みの時間帯、就業前後の時間に来院が固まってしまう可能性があります。
医療ドミナント
*メリット
隣接するエリアに医療機関が集まっているという状態なので、習慣のしやすさや医療連携のメリットがありつつも、個々の診療所は独立しています。そのため、設計やデザインの自由度がもっとも高いです。
*デメリット
医療ビレッジ同様に戸建てタイプになりますので、開業費用は他のタイプと比べて高くなります。さらに医療ドミナントの場合は基本的に共有施設もありませんので、医療ビレッジよりも開業費用が高くなることが多いです。
医療モールが増加しているその背景とは?
医療モールが増加している背景にはどんなことがあるのでしょうか? 「社会」「医師」「患者」のそれぞれの視点から解説します。
社会からの視点
日本は高齢化によって医療費が増加の一途を辿るようになりました。2021年度の国民医療費のうち国庫負担額は11兆4027億円で、国の一般会計歳出の1割弱が医療費に充てられている計算になります。OECDによると、日本の政府支出に占める公的医療費の割合は、OECD加盟国中で最も高いとのことです。このままでは「保険制度が崩壊しかねない」と危惧されています。
国は医療費増加を抑えるための対策として、高齢者に対しての不必要な入院を減らす目的で病床の数を減らし、介護施設や在宅での通院を促進しようとしています。これまで多くの患者を受け入れてきた中核病院は重篤および重症者の治療に対し高度な医療技術を提供し、診療所は地域の「かかりつけ医」として第一診療に携わる、とそれぞれの役割の分担を進めているのです。このように地域医療の充実を測る必要性がでてきたため診療所に求められる役割も変わってきており、診療所の業務だけではなく、在宅医療やリハビリテーション、介護施設との連携も必要となるなど包括的な医療活動が求められています。
その点、医療モールなら複数の診療科と専門性の高い医師が集合した医療施設タイプなので、モール内で連携を高め、地域医療の活性化を実現できるので、地域住民の注目も高まっています。
医師からの視点
少子高齢化が進む日本では年々人口が減少し、患者数も減少傾向にあります。しかし、医師の人数は増加傾向にあります。その一方で、前述の通り国は膨らむ医療費に対する対策として病床の数を減らす政策を打ち出しました。これにより、医師の人数は増加しているにも関わらず、病院の数が減少しているのです。その結果、医師の就職先が不足し開業医が増加することになりましたが、開業医同士の競争が激化している状況を引き起こしています。開業すれば必ず集患できる時代ではなくなっていることを考えると、きちんとした事業計画を練り、経営の効率化を図る必要があります。この状況の解決に適した一つの方法が、この医療モールという形態といえるでしょう。
患者さんからの視点
患者さんからみても、医療モールへの期待感はますます高まっています。
これまで病院に入院して診てもらえていた病気を在宅で治さなければならないということですから、不安も大きいです。医療モールが頼り甲斐のある地域医療として機能してくれれば安心につながるでしょう。また、本来なら別々の場所に通わなくてはならない疾患でも、同じ医療モール内で完結できるようになります。
さらには、医療モールは診療科の違う診療所同士でも患者さんの医療データを共有し、1枚の診察券で複数の診療科を受診できる連携システムが整っているので、患者さんにとっても大きなメリットとなりうるのです。
まとめ
高齢化による医療費の増大という社会問題によって引き起こされる課題を解決するための一つの方法として、さまざまな診療科が1つの場所で集患する形の「医療モール」は有効であるといえます。これから開業を目指す方にとっては、集患のしやすさはもちろんのこと、初期費用やランニングコストを削減するという点においてもメリットがあります。
医療モールの中でも、医療ビレッジ、医療モール、医療ビル、レジデンス併設型、オフィス併設型、医療ドミナントと様々なタイプがあります。それぞれに特徴があり、メリット・デメリットがありますので、自分が実現したい診療所のイメージ、現実的な費用や効率面などを含めて、どの医療モールが適しているのかを検討してみてはいかがでしょうか。